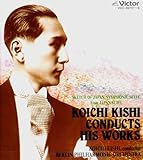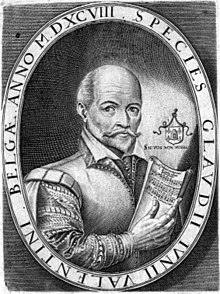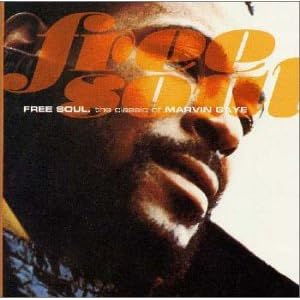こんにちは、仕事柄朝が早いので、朝目覚めるとまずラジオを聴きます。以前はテレビを付けていましたが、現在ではよほど気になる番組がある時のみで、それに代わって登場したのが深夜のラジオ番組です。といっても「オールナイトニッポン」などの番組を聞いていたのはもう遠い学生時代の話!今ではすっかりNHKの「ラジオ深夜便」に嵌っています。中でも2時台の「ロマンティック・コンサート」と、3時台の「にっぽんの歌こころの歌」はお気に入りです。「にっぽんの歌こころの歌」の方はアーティストや特集によって選択をしますが、「ロマンティック・コンサート」の方は月曜~金曜日までほぼ毎日聞いてるという状況です。
「ロマンティック・コンサート」は、採りあげる音楽のジャンルの幅の広さが大きな魅力です。クラシックの小品を扱うかと思えば、ジャズ・ジャイアントの名演、ロック史上に名を遺したグループや歌手、ソウルにレゲエ、そしてオールディーズにクロスオーヴァーとおよそ洋楽のあらゆるジャンルを網羅しています。学生の頃から親しんできたアーティストがいるかと思えば、初めて聞くアーティストも、御贔屓のアーティストの知らない作品に出会ったり、初めて聞くアーティストの音楽に感動することができた時にはやはり音楽を聴いてきて良かったとしみじみ思ってしまいます。
最近この番組で二人のアーティストの音楽に感動を受けましたーマーヴィン・ゲイとボブ・マーリー。この二人は言わずと知れたニューソウルとレゲエで巨大な足跡を残した世界的なアーティストですね!勿論彼らの名前と幾つかの作品は知っていましたが、「ロマンティック・コンサート」で特集された二人の作品ーマーヴィン・ゲイ:アルバム「ホワッツ・ゴーイング・オン」、ボブ・マーリ:アルバム「キャッチ・ア・ファイヤー」ーを聞いて甚く感銘を受けました。この2枚のアルバムはまた二人にとっても重要な転機になったものです。
「ホワッツ・ゴーイング・オン」はそれまでナット・キング・コールばりのエヴァー・グリーンのアルバムやラブ・ソングをリリースしていたマーヴィン・ゲイが、ベトナム戦争から帰還した弟から悲惨な戦場の話を聞いて、これまでとは方向を180度転回して「ベトナム戦争反対」や「公民権運動」といった社会問題をテーマにして制作したアルバムで、71年ーベトナム戦争が行われている最中に制作されました。当初モータウン・レコードは「問題あり」としてこのアルバムをリリースしようとはしませんでしたが、マーヴィンの強い意思もあり、結果として「ホワッツ・ゴーイング・オン」はモータウン・レコードからリリースされることになり、彼の名を一躍世界的なものにする大ヒットになります。マーヴィンの甘い歌声、そして完璧なまでのアレンジとサウンド、加えるにそのテーマの大きさ!このアルバムは現在でも彼の最高傑作としての地位を不動のものにしています。これ1作でマーヴィンは「ニューソウル」というジャンルを確立することになりました。
「キャッチ・ア・ファイアー」はボブ・マーリーが初めてメジャー・デビューを果たしたアルバムです。ウェイラーズを結成し、自らその一員となって活躍していたマーリーはメジャーレーベル、アイランド・レコードと契約し、73年にアイランド・レコードでの初アルバム、「キャッチ・ア・ファイヤー」をリリースし、世界的なヒットを記録します。マーリーとウェイラーズはこのアルバムで国際的な英雄となり、以後次々に傑作アルバムをリリースしていくことになりました。冒頭の「コンクリート・ジャングル」から終曲の「オール・デイ・オール・ナイト」まで大都会の抱える「憂い」と「闇」を歌い切るマーリーの歌声と彼らの作り出すレゲエのサウンドは深い感動を誘います。
ところでマーヴィン・ゲイとボブ・マーリーの二人には不思議な共通点があります。一つには二人ともに若くして世を去らねばならなかったことーマーヴィンは1984年、口論して激情した父親が彼に発砲してそのまま帰らぬ人に、享年44歳、またボブ・マーリーは以前から患っていたガンが足の親指に現れ、それが全身に転移して死去、享年36歳という若さでした。また二人の音楽もへヴィー・メタルやプログレッシブ・ロックのように大音響で絶叫することによってメッセージを伝えようとするものではなく、どこまでもサウンドは洗練され歌声はある種の優しさも持っています。それ故に却って彼らの社会性を持ったメッセージが今私たちが直面している日常的なものであり、極めて深刻なものであることが浮き彫りにされていきます。
今日は最後にマーヴィン・ゲイのアルバム「ホワッツ・ゴーイング・オン」から冒頭の同名作品と、ボブ・マーリーの「キャッチ・ア・ファイヤー」から第1曲の「コンクリート・ジャングル」をお届けしましょう。お楽しみください。
"What's Going On"
Mother, mother
There's too many of you crying
Brother, brother, brother
There's far too many of you dying
You know we've got to find a way
To bring some lovin' here today - Ya
Father, father
We don't need to escalate
You see, war is not the answer
For only love can conquer hate
You know we've got to find a way
To bring some lovin' here today
Picket lines and picket signs
Don't punish me with brutality
Talk to me, so you can see
Oh, what's going on
What's going on
Ya, what's going on
Ah, what's going on
In the mean time
Right on, baby
Right on
Right on
Mother, mother, everybody thinks we're wrong
Oh, but who are they to judge us
Simply because our hair is long
Oh, you know we've got to find a way
To bring some understanding here today
Oh
Picket lines and picket signs
Don't punish me with brutality
Talk to me
So you can see
What's going on
Ya, what's going on
Tell me what's going on
I'll tell you what's going on - Uh
Right on baby
Right on baby
「ホワッツ・ゴーイング・オン」
母さん、母さん、
あなたは尽きることなく涙を流している。
兄弟よ、兄弟よ、
みんな遠くであまりに多くの命を落としている。
何か方法を見つけなくちゃならない。
今日ここに愛をもたらす方法を。
父さん、父さん、
もうこれ以上エスカレートしてほしくない。
わかってるはずだ。戦いは解決にならない。
憎しみを克服できるのは愛だけだ。
何か方法を見つけなくちゃならない。
今日ここに愛をもたらす方法を。
デモ隊の行列。
スローガンの数々。
僕を押さえつけないでくれ。
暴力なんかで。
話し合おう。
そうすればわかるはずだ。
ああ…何が起こっているんだ?
何が起こっているんだ?
ねぇ、何が起こっているんだ?
ああ…何が起こっているんだ?
母さん、母さん、
誰もが自分は悪くないと考えている。
ああ、でも誰が裁くというんだい?
単に僕らの髪の毛が長いという理由?
ああ、何か方法を見つけなくちゃならない。
今日ここに理解をもたらす方法を。
デモ隊の行列。
スローガンの数々。
僕を押さえつけないでくれ。
暴力なんかで。
こっちに来て話し合おう。
何かがわかるかも知れない。
何が起こっているんだ?
ねぇ、何が起こっているんだ?
教えてくれ。何が起こっているんだ?
あなたが何をしているのか教えてあげよう。
"Concrete Jungle"
No sun will shine in my day today (no sun will shine)
The high yellow moon won't come out to play
(that high yellow moon won't come out to play)
I said (darkness) darkness has covered my light,
(and the stage) And the stage my day into night, yeah.
Where is the love to be found? (oh-oh-oh)
Won't someone tell me?
Cause my (sweet life) life must be somewhere to be found
(must be somewhere for me)
Instead of concrete jungle (la la-la!),
Where the living is harder (la-la!).
Concrete jungle (la la-la!)
Man you got to do your (la la-la!) best. Whoa, yeah.
No chains around my feet,
But I'm not free, oh-ooh!
I know I am bound here in captivity;
G'yeah, now (never, never) I've never known happiness;
(never, never) I've never known what sweet caress is
Still, I'll be always laughing like a clown;
Won't someone help me? 'Cause I (sweet life)
I've got to pick myself from off the ground
(must be somewhere for me), he-yeah!
In this a concrete jungle (la la-la!)
I said, what do you cry for me (la-la!) now, o-oh!
Concrete jungle (la la-la!), ah, won't you let me be (la la-la!), now.
Hey! Oh, now!
I said that life (sweet life) it must be somewhere to be found
(must be somewhere for me)
Oh, instead, concrete jungle (la-la!) collusion (la-la!)
Confusion (confusion). Eh!
Concrete jungle (la-la!) baby, you've got it in.
Concrete jungle (la la-la!), now. Eh!
Concrete jungle (la la-la!).
What do you stand for me (la-la!), now?
「コンクリート・ジャングル」
俺の一日は お日様が輝かないだろう
高い 黄色いお月様は 遊びに出てきてくれないだろう
暗闇が 俺の明かりを覆ってしまうと 言ってるのさ
そして 俺の一日を 夜に変えてしまうんだ
何処で 愛を見つければいいんだい?
誰か教えてくれないかい?
人生を 何処かで見つけなきゃならないから
コンクリート・ジャングルの他には
何処で暮らすのが ハードかな?
コンクリート・ジャングル
お前は ベストを尽くし始めた
俺の足には 鎖はついてないが
俺は 自由じゃない
ここに囚われて 制限を受けている
幸せなんか 知らないよ
甘美な愛撫なんて 知らないよ
それでも いつものように ピエロみたいに笑うんだ
誰か 助けてくれないか? 何故なら 俺は
地に足を降ろそうとしているから
この コンクリート・ジャングルで
お前は 今 何を得たんだ?
コンクリート・ジャングル
その人生は それは 探せば何処かにあるはずだ
コンクリート・ジャングルの他には
幻想 混乱
コンクリート・ジャングル お前は その中へ漂着したんだ
コンクリート・ジャングル
コンクリート・ジャングル
お前は 今 何を得たんだ?
日本語訳は以下のサイトから引用させて頂きました。